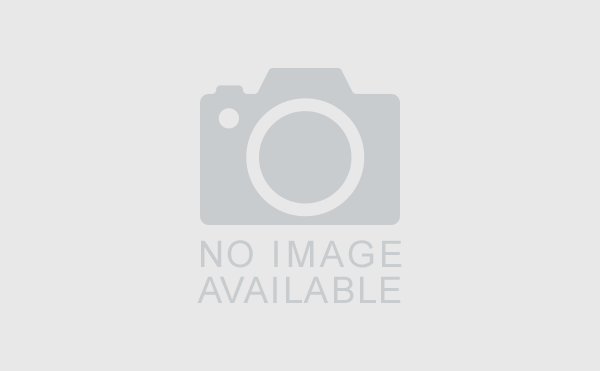「京都府立植物園・京都園芸倶楽部共催第64回つばき展・箱田会長講演」報告
3月23日(日)午後、京都園芸倶楽部の第1244回例会として、日本ツバキ協会・箱田直紀会長による「京の銘椿と原種ツバキ」公開講演会が開催されました。

日本で最初の公立植物園として1924年に開園した京都府立植物園は、昨年創立100周年を迎えました。挨拶をされる戸部博園長です。「いつもの例会とは、受講者の顔ぶれが違いますね」とのこと。幅広い層のツバキ愛好者が駆け付けたようです。

京都府立植物園より一年早く、2023年に創立100周年を迎えた京都園芸倶楽部の畑山裕子会長。通算1244回という驚異的な例会回数の多さが、活動歴の長さを物語っています。

原種ツバキについて講演する箱田会長。50枚近いスライドを使いながら、日本原産の4種のツバキ属植物に始まり、中国、ベトナム、フィリピンやインドネシアのツバキまで、原種ツバキの植物学からツバキ属植物利用の経緯、自生地の状況まで、幅広い話がありました。京都の寺社に咲く園芸品種のツバキについても話をされました。
最後に、薬学博士でツバキ研究家であった故渡辺武氏のことに言及しながら、こう締めくくられました。
「皆さんにお願いがあります。生前渡辺先生は、多くの協力者と共に日本全国をくまなく歩き、各地の銘椿・古木等を調査し、貴重な記録を残されました。渡辺先生が亡くなられて既に20年が経ちます。これから30年ほどかけて、京都園芸倶楽部さんや日本ツバキ協会の支部とも連携しながら全国的に改めて調査をし、新しい記録を残す必要があります。是非、ご協力をお願いします」
箱田先生の提言、しかと受け止めたいと思いました。
小島信江理事・広報部長からの報告です。 (令和7年3月29日)